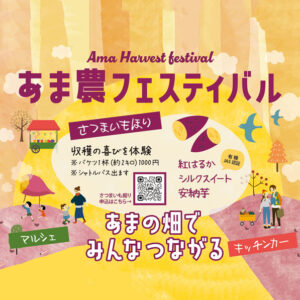活動レポート
至極の一皿 第三章〜記憶〜「農福」

現代の日本が抱える大きな課題の一つに、農業の後継者不足があります。高齢化が進む中で、農業従事者が年々減少し、耕作放棄地も増加しています。
一方社会福祉分野では、障がい者の就労先が限られており十分な雇用機会が確保されていないのが現状です。この問題を同時に解決しようとする取り組みが国が掲げる「農福連携」です。
しかし、この国家プロジェクトでは根本的な問題が解決されていませんでした。
問題なのは「経済の循環」です。
愛ふぁーむプロジェクト正会員のお店では、障がい者が生産した野菜をお店で使用する事で「農福食の連携」を実現しています。これにより、農福連携で生まれた野菜が単なる流通品として終わるのではなく、シェフ達の創意工夫を通じて社会に広がり、消費者に届く仕組みが確立されつつあります。
シェフ達が心を込めて作る料理は、障がい者が手塩にかけて育てた野菜の価値をさらに高め、食を通じて農福連携の意義を社会に広く伝える役割を果たしています。来店されたお客様はその料理を味わい、野菜の美味しさを実感する。そして、その売上が障がい者の給料となり経済が回る。
この仕組みによって、障がい者が単なる生産者としてではなく、「食の価値を提供する担い手」として社会に参加できるようになるのです。
このように「農福連携」に「食」をプラスした「農福食連携」により、障がい者の就労支援が消費者と直接つながる経済循環モデルが「愛ふぁーむプロジェクト」です。葛原シェフはこのプロジェクトを計画した時、誰よりも早く参加表明してくれました。
このメニューは障がい者の方達が愛情込めて大切に育てられた野菜達の香りや食感を最大限に活かす様、茹で、揚げ、焼き等の様々な調理法で下処理し、特製のソースをかけ温かいスープ仕立てのサラダにしています。器は富山の陶芸作家 釋永岳氏にこのメニューの為だけにオーダーしてくれました。
葛原シェフがこの社会問題にクローズアップし、食の社会的意義を想って作られた至極の一皿
第三章〜記憶〜「農福」
みなさま是非食して、この「あたたかさ」を体感して下さい。